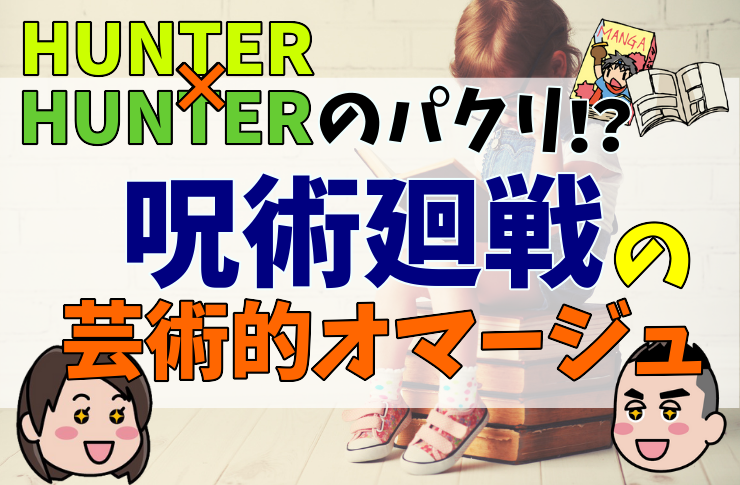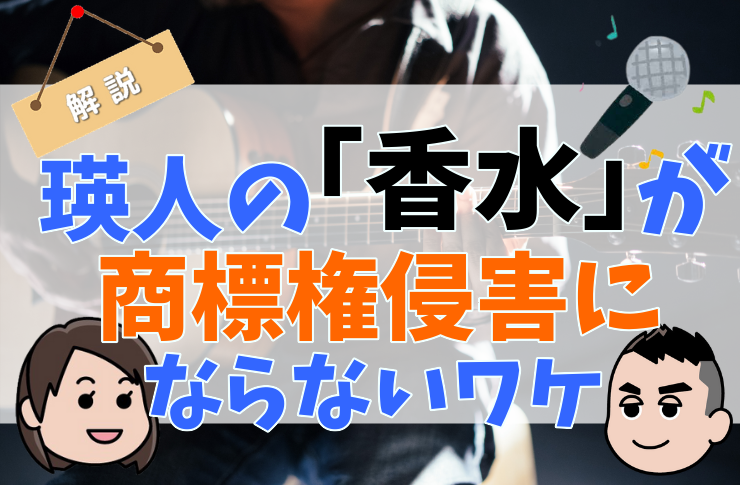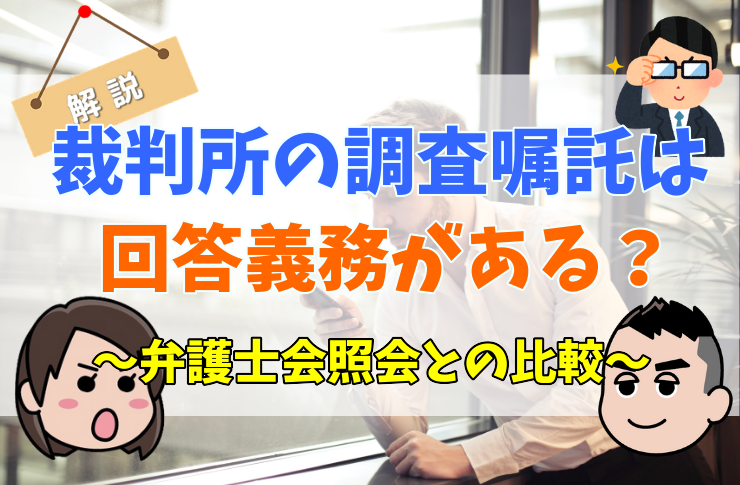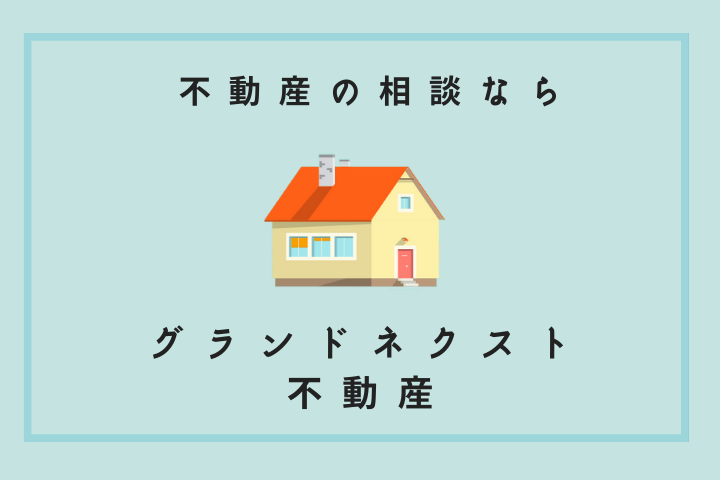離婚の紛争において、お金のことで一番問題となるのが財産分与です。
裁判離婚問題において、慰謝料がひどい不倫等があった場合でも、せいぜい300万円以下ぐらいになってしまいます。そこで、今後の人生に備えて大きな金額を確保したいのであれば、夫婦生活でできた財産を分け合う「財産分与」をしっかりと進めていく必要があります。
夫婦財産が多い場合には、なおさら財産分与に力を入れる必要があります。
そこで、
①財産分与の財産はどの範囲が基準となるか?
②どのような財産が財産分与の対象となるか?
等について解説します。
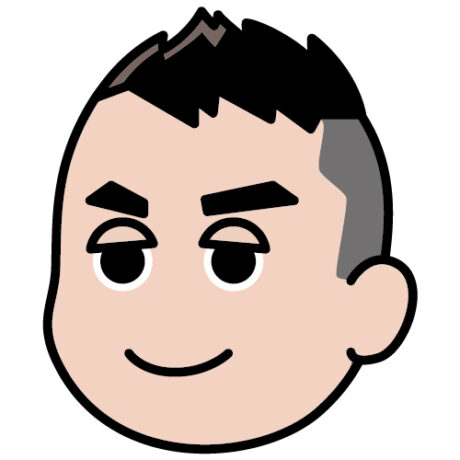
中央大学の法務全般を担当している中央大学「法実務カウンセル」(インハウスロイヤー)であり、千代田区・青梅市の「弁護士法人アズバーズ」代表弁護士、櫻井俊宏が執筆しております。
1 財産分与の基準時はいつなのか?
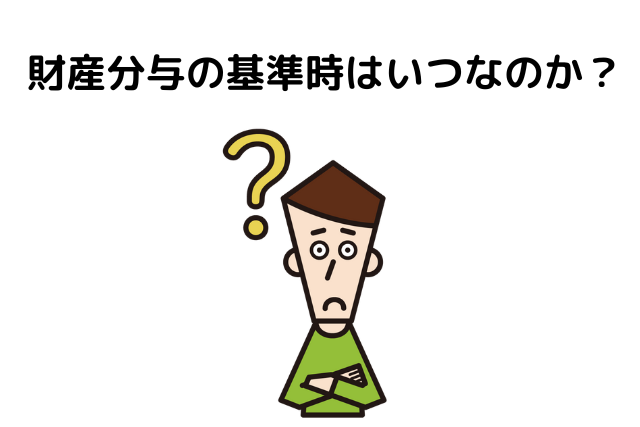
日本では夫婦の財産は別々となっていますが(「夫婦別産制」といいます。民法762条。)、結婚時から離婚時までに形成された夫婦の財産は、原則として半々に分け合うのです。
財産分与の2分の1ルールについて
て半厳密にいうと夫婦の「同居時から別居時」です。
このことからすると、夫婦の関係が既に悪くなっていて、例えば、夫が、財産分与上自分の利益になるように、財産をこっそりどんどん使われたり、隠されたりされそうな場合には、妻は早めに自分から家を出て別居をした方がよいということになります。
別居時が確定すれば、その後に使われてしまった財産は、財産分与では考慮されないからです。
例えば、一度、別居時に夫が管理する金額が1000万円、妻が管理する金額が500万円という状態が確定すると、それを750万円ずつ分け合うのが原則となります。
その金額で固定されるイメージで、それ以降に両者が使ったり、入金されたお金は、財産分与の計算の基準に入りません。
預金や生命保険の解約返戻金等の財産を隠されそうになった場合には、裁判所に申し立てて、裁判所から銀行や保険会社に命令をしてもらい、預金や保険を動かせなくする仮差押等の「保全処分」が有効です。
【参考記事】離婚の財産隠しに対抗 仮差押
なお、「別居することを言い出しにくい」といった相談を良く聞きます。
しかし、自分から家を出ていって別居したとしても、法的に生活費(婚姻費用)をもらう権利は存在するので、不利とはなりません。
下記の記事参照。
【参考記事】自分から別居した場合も生活費(婚姻費用)がもらえる?
相手方が不倫やDVを行っている等の離婚理由がない場合、強制的に離婚するには別居期間を5年以上積み重ねる必要があります。
このことからしても、別居がはじまらないとなかなか離婚には至らないのであり、できるのであれば思い切って別居をまずする必要があります。
2 財産分与の対象とはならない特有財産について
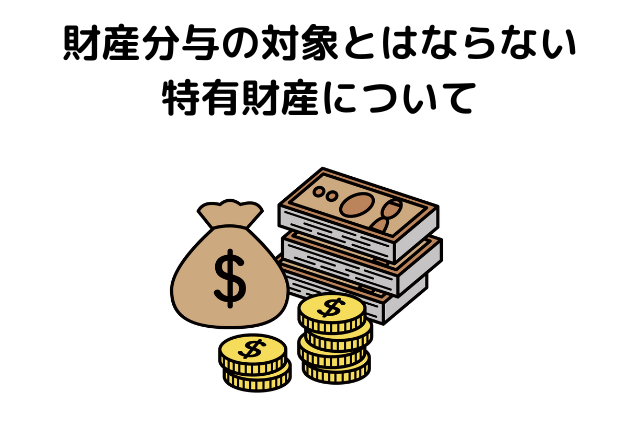
例えば、「結婚したときの同居時に自分は300万円持っていて、別居時に1000万円持っているから、夫婦生活によって増えた分は700万円に過ぎない!」
と主張するのであれば、同居時に300万円持っていたことを、当時の預金通帳等を証拠で示して、自分で証明する必要があります。
この300万円は財産分与の対象とはなりません。
これを「特有財産」といいます。
預金通帳の取引履歴は銀行に取り寄せても10年分ぐらいしかデータが残っていないので、結婚時の預金の残高がわかる通帳等は、万が一離婚ということになったときのために捨てずに残しておいた方がよいということになります。
なお、親から相続した財産も特有財産に入ります。
そうだとすると、相続分についても証明できるように、相続財産も現金手渡しではなく、預金通帳に振込等の履歴を残しておいた方がよいということなります。
この特有財産の立証は厳密なものが必要です。
特に、株式等の場合には、ある証券会社に入れてある投資用財産が結婚時にあって、離婚時にあればよいというものではなく、基本的には、「同じ会社の株式」が、結婚時と離婚時に同じ数量あるということまで要求されます。
3 財産分与の対象財産
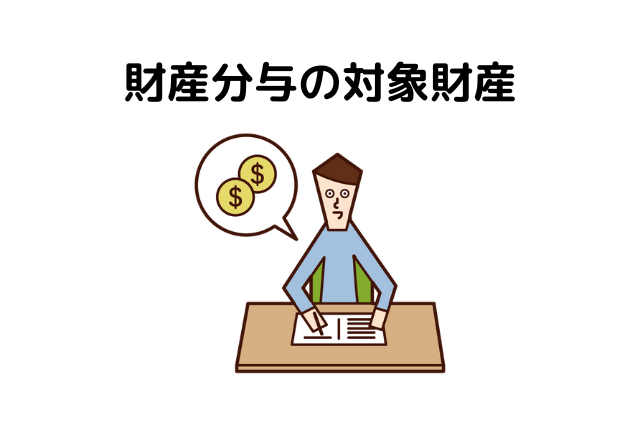
夫婦の同居中に形成された、務めていた会社の退職金は財産分与の対象となるでしょうか?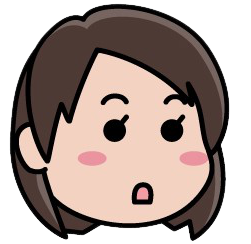
これは、原則財産分与の対象財産となります。
しかし、退職金に関しては、必ずしも全て対象になるとは限りません。
退職金の財産分与についての記事はこちら
相手方が、他の自分の口座等に振り込む方法等で財産隠しをされた場合に、他の通帳に移した履歴が残っていれば、振込先の隠し口座等を開示してもらい、財産隠しをあばくことができます。
もっとも、それをするには、裁判所を利用して開示してもらう手続(文書送付嘱託や調査嘱託)でないとなかなか難しいです。
文書送付嘱託や調査嘱託についての記事はこちら
文書送付嘱託や調査嘱託は、相手に預金口座が存在することがわかっていても,くこ金融機関の支店名まで発覚していないと、後々その口座の口座番号や残高等の内容を開示してもらうことはできません(ただしゆうちょ銀行は支店名までわからなくても大丈夫です。)。
そこで、配偶者と別居をするときは、相手の【預金口座の金融機関・支店】の情報をおさえておく必要があります。
その他、不動産はもちろん、生命保険や証券、自動車も財産分与の対象となります。なお「年金分割」といって、同居していた期間に積み立てられた厚生年金等の公的年金も半々に分けることができます。
まずは、別居をする際には、こっそりでもいいので、相手方の財産を示す資料の写し又は写真を集めておきましょう。
4 ローン等の債務は財産分与の対象となるのか?
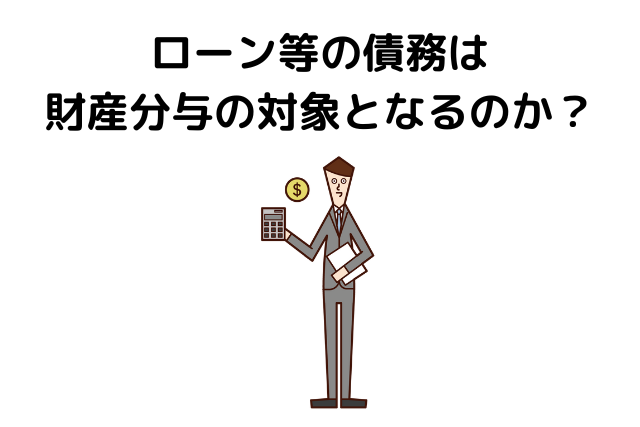
債務、すなわち借金については財産分与で分け合うことになるかどうかということに関しては、「分け合わない」というところが原則です。
しかし、借金がプラスの財産とひもづいている場合等は、財産分与の対象となる借金もあります。
詳しくは下の記事で解説しております。
【参考記事】借金はどのように財産分与されるのか
また、住宅ローンについては、まさにプラスの不動産にひもづいた借金として、原則として財産分与の対象としてカウントされますが、
その不動産を売却するのかどうか、誰が住んで誰が今後ローンを支払っていくか、
など、更に難しい問題をはらんでおります。
下記の記事を参考にしていただければと思います。
【参考記事】家の財産分与はどのように行われるか
まとめ
このように、離婚をする場合、紛争に備えて、財産分与を意識した初期行動をとる必要があります。
これができないと、実際の紛争になった際、相手方にイニシアチブをとられ、他の条件等も悪い条件を押し付けられることもしばしばです。
特に子供の養育権を持つ側は、今後の子供の生活のことも考えて、しっかり自分が本来もらえる財産は確保すべきだと思います。