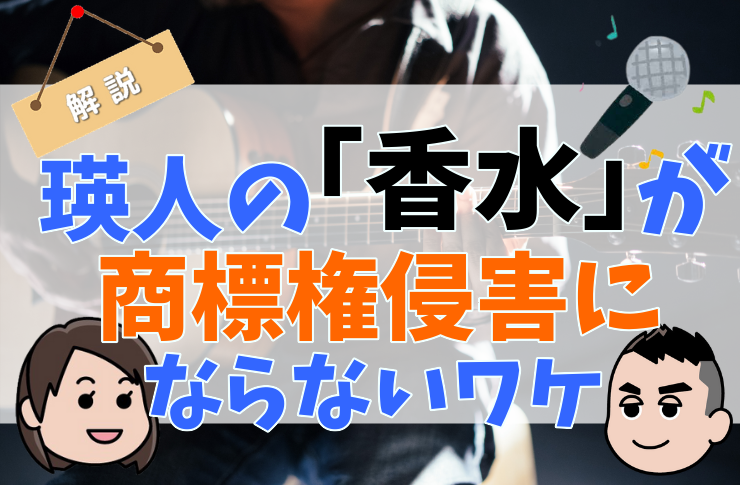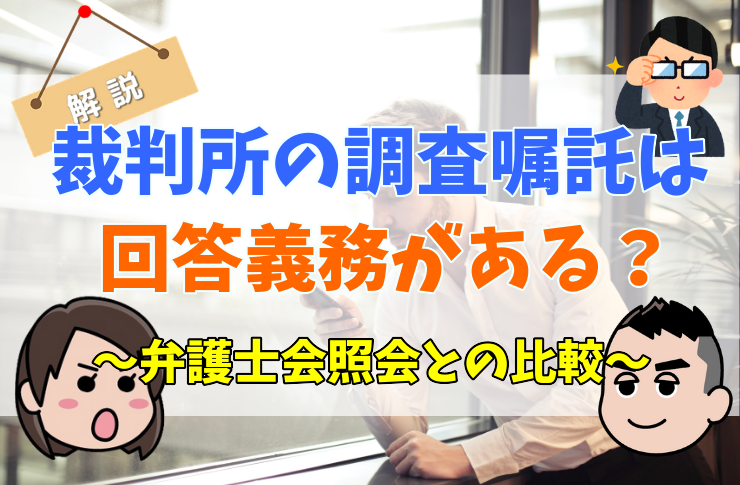遺産分割協議withコロナ”と状況が変化し、久しぶりに帰省したという方も多いのではないでしょうか?
再会の喜びも束の間、「物忘れが多い」「怒りっぽくなった」と親の変化に戸惑ったのであれば、相続対策を急ぐ必要があります。
本記事では、
・認知症の家族を守るための遺言
・認知症の相続人を無視した相続手続きのリスク
・認知症の相続人が遺産分割協議に参加する方法
・認知症の方の遺言
について解説していきます。
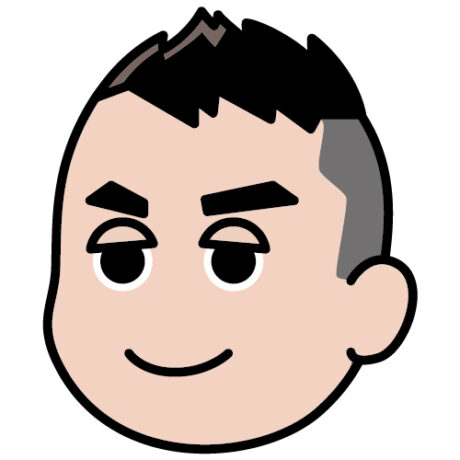
学校法人中央大学の法務全般を担当している中央大学「法実務カウンセル」(インハウスロイヤー)であり、千代田区・青梅市の「弁護士法人アズバーズ」代表、弁護士の櫻井俊宏が執筆しております。
1 「認知症の親が」相続する場合

父が亡くなり、判断能力の低下した母と子が相続人になったような場合です。
(1)遺言がある場合
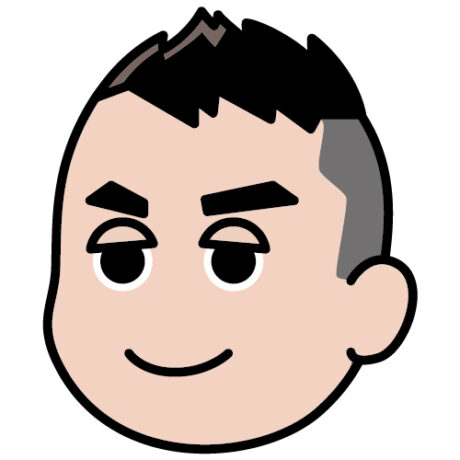
父が生前に遺言書を準備していた場合を想定しましょう。
① 遺産分割協議は不要
判断能力が低下した人にとって、遺産全体を把握して自分にとっての要否を判断し、かつそれを他の相続人に掛け合うのは非常にハードルが高く、できれば協議すること自体を避けたいものです。
そこで、被相続人が遺言書を準備することからスタートです。遺言があれば基本的にはその通りに財産が分けられますので、遺産分割協議がいりません。
② 法的手続きが難しい相続人のための対策
遺言書なら何でもよいわけではなく、能力や行動に制限がある相続人のことを考えたものにすべきです。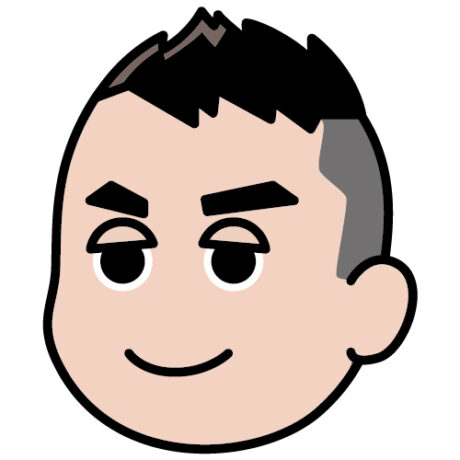
③ 遺言執行者の指定
相続人が実際に財産を取得するには様々な手続きをしなくてはなりません。たとえば、不動産の所有権移転登記手続きや売却による換価手続き、預貯金や有価証券の解約・相続手続きといったものです。これらの手続きには多数の書類を取寄せて内容を確認の上署名・捺印、そして提出が求められます。判断や身体能力が低下した相続人には難しい作業になるでしょう。
そこでスムーズな相続を実現するために、遺言する際には遺言執行者の指定をしておきましょう。遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする単独ですることができるのです。
「誰が」についてですが、民法1009条で「未成年者及び破産者」はなることができないと規定されている以外に制限はありません。したがって、被相続人のご家族、つまり同じ相続人の中から選ぶこともできます。ただし、財産が多い、相続人同士が疎遠であるといった場合には、業務内容が複雑なので、弁護士等の専門家に任せるのが賢明でしょう。
(2)遺言がない場合
生前の父による遺言がなく、判断能力の低下した母と子が相続した場合はどうでしょう?
① 子が単独で諸手続きをするのはNG
母の認知症が重く意思表示ができない場合に、「いずれ自分のものになる」「黙っていればバレない」と考え、勝手に母名義で署名捺印をするなどして単独で相続手続き進めてはいけません。
まず、相続人の認知症は隠し通せるものではないことを確認して下さい。相続税の支払いや認知症本人の医療費等の工面のため、銀行窓口での預金払戻しや不動産の売却といった場面では必ず本人確認が求められます。取引に入る金融機関や司法書士らが法的責任のリスクを背負いながら確認作業にあたるため、少しでも疑念が生じた場合には取引はストップします。
② 損害賠償責任が発生することも
仮に取引が一旦成立したとしても母から代理権を与えられていない以上、子が母名義で行った法律行為は無権代理として無効になります。その後、改めて選任された成年後見人が無効行為の追認を拒絶した場合は、勝手に行為をした子は相手方に対して損害賠償責任を負わなければなりません(無権代理人の責任、民法117条)。
それだけではありません。契約書や証書等に許可なく母名義で署名する行為は有印私文書偽造罪(刑法159条1項)に、その書類を提出する行為は同行使罪(161条1項)が成立する恐れもあります。
軽い気持ちで認知症の家族名義で署名等を行うと、このような重大な法的責任が発生することに留意して下さい。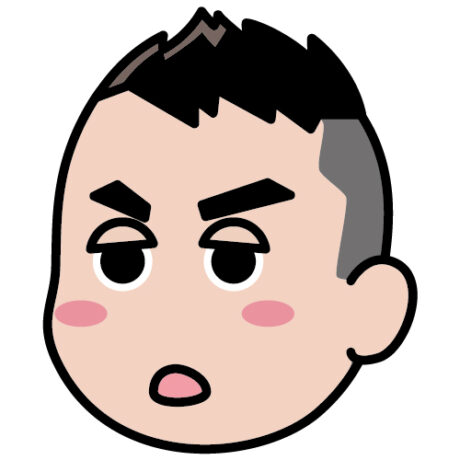
2 法定相続分通り、もしくはそのまま放置することのリスク

では、法定相続分通りに分けるのはどうでしょうか?
上記例だと、母と子はそれぞれ2分の1ずつ共有することになります。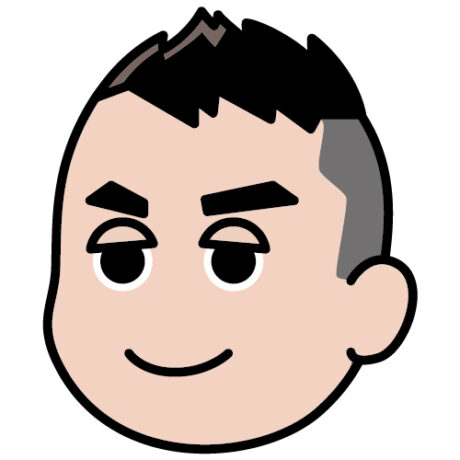
法定相続分に従うのであれば遺産分割協議は不要であり、かつ子は自身の持ち分について自由に処分することができるようになるため、一見、簡便で合理的な方法にも思えます。
しかし、このような分け方は自宅内に多額の現金を保有しているといった特殊な事情のない限り、あまり意味のある方法ではありません。
不動産
共有状態の不動産は共有者全員が合意しないと処分することができません(民法251条)。建物であれば解体や増改築、土地であれば造成や分筆、さらにこれらを売却できません。また、持分の過半数の同意がないと賃貸することもできないのです(民法252条)。理論上は自己持分のみを売却することも可能ですが、極端な安値となることも覚悟しなければならず、売却できたらできたで、他の相続人が第三者と共有になるというイレギュラーな事態を招き、トラブルの原因にもなりえます。当該不動産に見合った価格で売却するには、結局相続人全員の合意が必要になります。
預貯金
2019年の民法改正により「仮払い制度」が導入され、それまで遺産分割協議を経なければ一切払い戻しができなかったのが、「150万円」または「当該銀行にある預貯金額×3分の1×法定相続分」のいずれか少ない額について払い戻すことが可能になりました(民法902条の2)。
この制度の目的は被相続人の葬儀や病院代に充てる費用を捻出するために相続財産から「仮に」払うというものです。したがって、仮払いを受けた金銭も含めて後日、改めて遺産分割協議をする必要があるのです。
そのまま放置
何もせずに放置するという方法もあります。これも、特に不動産についてはお勧めできません。
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があり、怠った場合は10万円以下の過料が科せられることになります。施行日以前に発生した相続についても、2024年4月1日から3年経過後も正当な理由がなく申請を怠ったときは罰則の対象になってしまいます。
遺産分割協議
結局、遺言がなければ全相続人で遺産分割協議をして財産を分けるというのが現実的です。
では、相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割協議はどのように進められていくのでしょうか?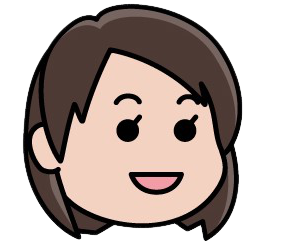
認知症でも遺産分割協議に参加できる?
遺産分割は各相続人に財産移転の効果が生じる法律行為ですから、通常の取引と同様、自分の行為が法的にどのような結果を生じさせるのかを理解できる能力(意思能力)が必要です。
認知症の程度がひどく、判断能力を欠いた状態にある相続人は意思表示をすることができません。したがって成年後見を受けていない場合であっても、このような方は遺産分割に参加することはできません。
一方で、多少の物忘れはするものの日常生活に支障がない軽度の場合は、必ずしも意思表示できないとは限らず、協議参加が可能なこともあります。その場合は後日協議の効力をめぐって争いにならないように、弁護士等の実務家がご家族から状況をヒアリングした上で、ご本人にとっての有利・不利等も含めて協議全体を考慮し、ご本人の意思の確認後、協議書を作成するというケースもあります。
このように認知症の程度や遺産の種類、協議内容に応じて慎重に判断する必要があります。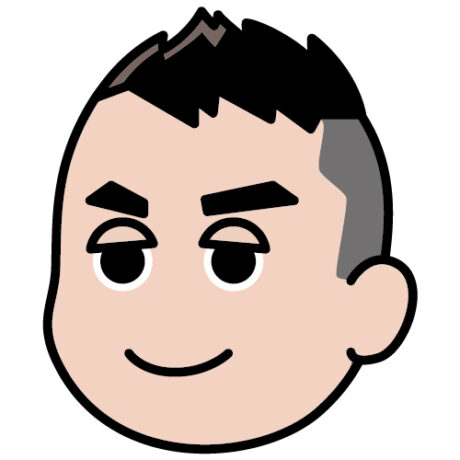
判断能力が低下した相続人のための対策
相続人が認知症であってもその方に代わって遺産分割協議に参加する、それが成年後見人です。
成年後見人には本人が判断能力のあるうちに将来の後見人を予め決めておく任意後見人と、意思能力を失った後に裁判所が選任する法定後見人があります。いずれも後見人として遺産分割協議をすることができますが、後見監督人や家庭裁判所の監督を受けます。
3 成年後見人とは

前述したように、成年後見人には2任意後見人と法定後見人があります。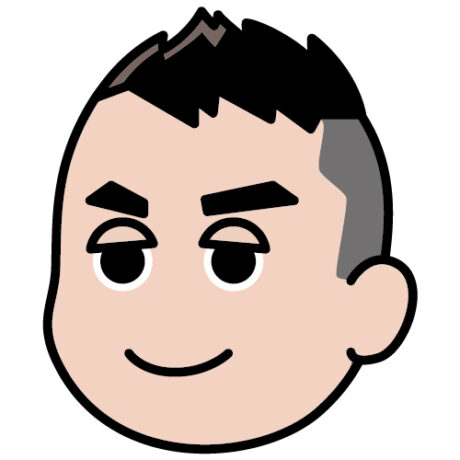
任意後見人
遠縁の親族や友人等、相続人の立場にない他人が任意後見人である場合は問題ありませんが、「子が母の任意後見人」のように両者が相続人同士の場合、子が母を代理しつつ自己に有利な協議を成立させる恐れがあります。そこで、子が相続放棄した上で母の任意後見人として諸手続きをとる、あるいは後見監督人(選任されていなければ特別代理人)が母の代理人として子と遺産分割協議をする、のいずれかを選択することになります。
法定後見人
選任申立時には候補者を挙げることができます。日頃から懇意にしている弁護士、司法書士等を候補者として挙げれば、候補者自身が記載する「候補者事情説明書」等の書面を裁判所が検討して問題ないと判断した場合には、その専門家が後見人に選ばれます。
また、親族でも法定後見人になれる場合があります。同じ相続人や貸し借りのある間柄といった例外*はありますが、身内だからこそできる本人に寄り添った後見を希望するのであれば弁護士等に推薦状を書いてもらうとよいでしょう。
4 認知症の親から相続する場合

認知症の親が遺言書を作成して死去した場合の相続はどうでしょうか?
(1)認知症でも遺言書を作成できる?
遺言は上述の遺産分割協議とは違って「交渉」という要素は含まず、本人の真意に基づくという点が重要な法律行為です。したがって、遺言に要する意思能力は高度である必要はなく、成年被後見人であっても一時的に判断能力を回復している時に医師2人以上の立ち会いがあれば遺言できます(民法973条1項)。
(2)遺言の無効を主張する場合はその立証が必要
問題が多発するのは成年後見が開始されていない人の遺言です。アルツハイマー型認知症では個人差はありますが、10年ほどかけて進行していきます。どの時点で後見を開始したのか、あるいは最期まで成年後見人を付けなかったというケースも少なくなく、遺言当時の意思能力が大きな問題となります。
裁判にまで発展した場合、遺言の無効を主張する側が遺言当時本人に意思能力がなかったことを立証しなければならず、立証がなければ遺言書は有効と扱われます。
証拠には次のようなものがあります。
・遺言の内容(複雑か、合理性があるか)
・長谷川式認知症スケールの点数
・医療、介護記録
・筆跡の乱れ
・公正証書作成時の意思疎通の様子 等
(3)遺言が無効にならないための対策
家族を「争族」にしないためには上記の証拠を万全にしておくのが理想ですが、ご本人が準備しておくには限界があります。そこで遺言書を作成する場合は、少なくとも公正証書方式で行う、医師による「認知症の疑いはない」旨の診断書をもらっておく、というように、信頼ある第三者の関与を残すという点を優先させて下さい。
5 まとめ
 65歳以上人口の6分の1が認知症を発症する現代において、認知症の方が相続人になる場合も被相続人になる場合も「早め」「遺言」がポイントです。
65歳以上人口の6分の1が認知症を発症する現代において、認知症の方が相続人になる場合も被相続人になる場合も「早め」「遺言」がポイントです。
どのようなスタイルの遺言が適切か、当事務所の弁護士が親身になってお答えします。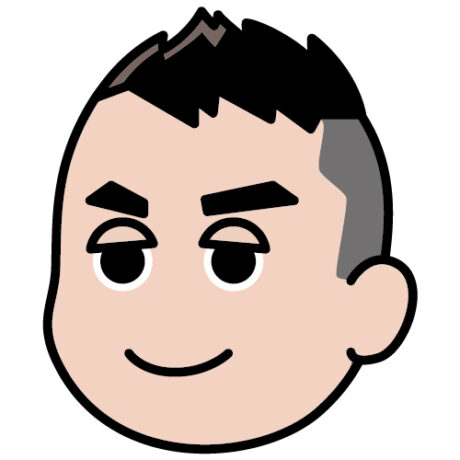
幻冬舎GOLD ONLINE 身近な法律トラブル