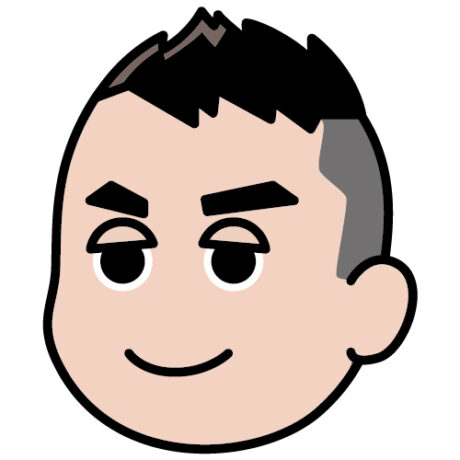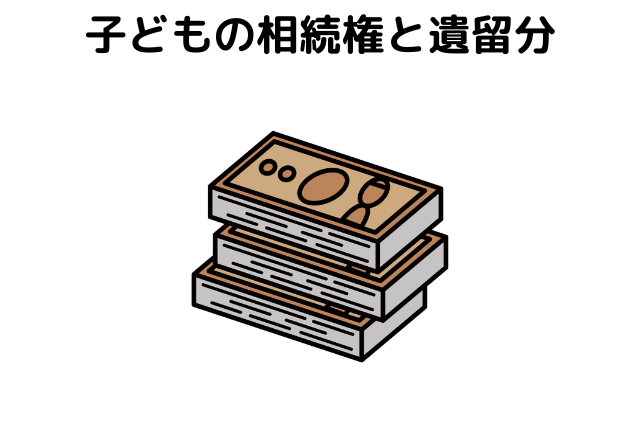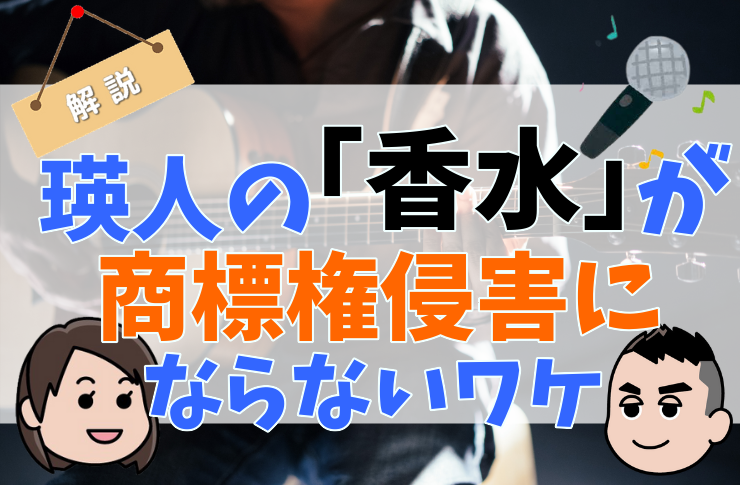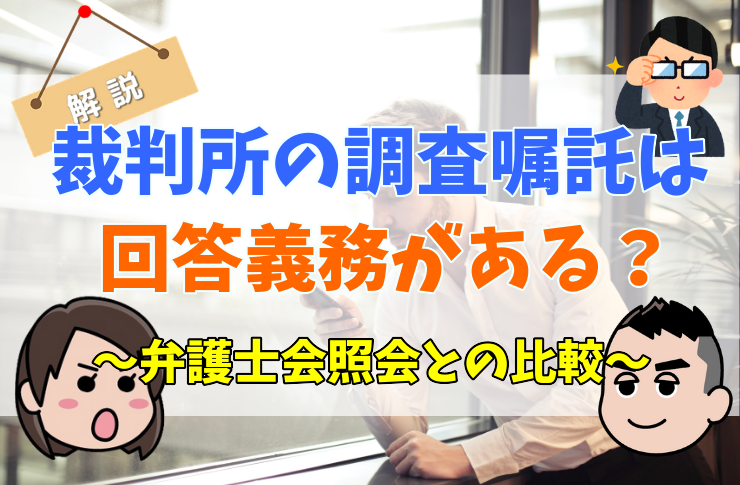自分の子どもに相続させたくないと考える方は意外といらっしゃいます。その背景には親子の関係や歴史が複雑に絡み合い、そして将来への展望もあります。
本記事では、まず
・相続させたくない理由
を探り、
・子どもの相続権と遺留分
について基本事項を確認します。
そして、後半ではケース別に具体的な方法として
・廃除
・遺言
・遺留分放棄
・遺留分に関する民法の特例
についても解説していきます。
学校法人中央大学の法務全般を担当している中央大学「法実務カウンセル」(インハウスロイヤー)であり、千代田区・青梅市の「弁護士法人アズバーズ」代表、弁護士の櫻井俊宏が執筆しております。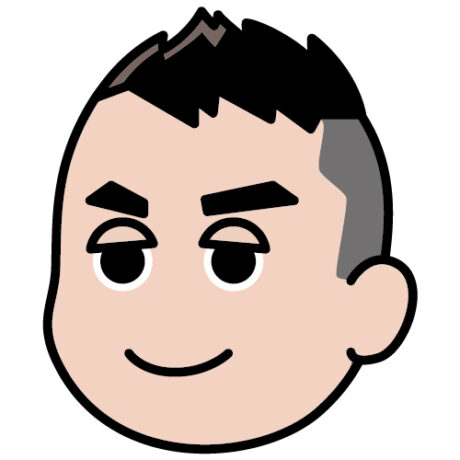
子どもに相続させたくない理由

考えられる理由には様々なものがありますが、大きく分けると次の3つです。
〇前妻の子
前妻との離婚後子どもと連絡をとっていない場合や、前妻が再婚しその再婚相手と養子縁組をした場合など、親子の実体や愛着が薄れてしまったことが理由と考えられます。
〇不仲
暴力、浪費、侮辱といった子ども側に原因のある場合だけでなく、性格が合わないという親子間の相性が理由になることもあります。
〇事業承継
相続を利用した事業承継では、事業用財産や株式等を法定相続分通りに各相続人に分けてしまうと事業がままなりません。そこで他の子どもには会社財産を相続させずに、後継者となる子どもに集中させることで円滑な事業承継を実現するという実益的な理由です。
子どもの相続権と遺留分
まず子どもの相続について確認しましょう。
子どもの相続権
子どもには親の相続財産についての相続権があります(民法887条1項)。
たとえ親権を失った子どもであっても、普通養子縁組をした子どもであっても、不良息子(娘)であっても、事業承継に参加しない子どもであっても、生物学的な親子である限りは相続人となります(特別養子縁組では親子関係終了)。
子どもの遺留分
遺留分とは法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められた最低限の遺産の取り分です。相続における相続人間の平等を図り、遺された家族の生活を保障するという機能もあります。法律上認められた権利であり、被相続人もこれを否定することはできません。つまり遺言等で一部相続人の遺留分を害する内容の指定をしても、当該相続人は侵害額を他の相続人に支払い請求できるのです。
そして相続権のある子どもにはこの遺留分もある以上、特定の子どもに「びた一文渡さない」ことは、法律上難しいことになります。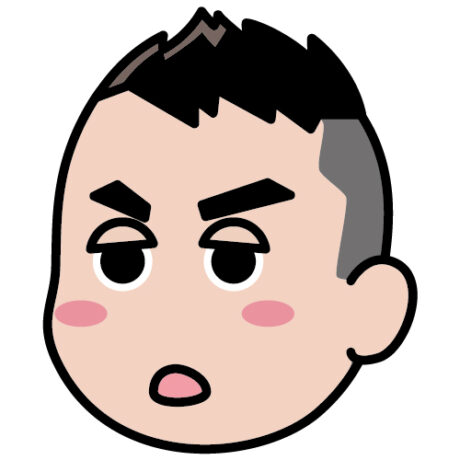
|
相続人
|
法定相続分 |
総体的遺留分
|
|
| 配偶者 | 子 | ||
|
配偶者と子(1人)
|
1/2 | 1/2 | 1/2 |
|
配偶者と子(2人)
|
1/2 | 1/4ずつ | 1/2 |
| 子のみ(1人) | 1 | 1/2 | |
| 子のみ(2人) | 1/2ずつ | 1/2 | |
遺留分侵害額は次の計算式から算出します。
| 遺留分額 |
|
基礎財産額×総体的遺留分×法定相続分
|
| 遺留分侵害額 |
|
遺留分額-(遺留分権利者の遺贈額+特別受益額+具体的相続分に応じた取得財産価格)+遺留分権利者が負担する債務
|
【ポイント】
複雑ですが、注目すべきは基礎財産額に遺留分や相続分の割合を乗じて遺留分額を算出し、そこから特別受益額等を控除したものが遺留分侵害額であるという点です。そこで遺留分侵害額を減らすには基礎財産額(相続開始時の遺産総額)を小さくし、遺留分権利者への生前贈与(特別受益額)を確実に差し引くことが重要になります。
【ケース1】前妻の子ども

特定の子どもの取得分(遺留分を含む)をできるだけ少なくするにはどのような方法があるのでしょうか。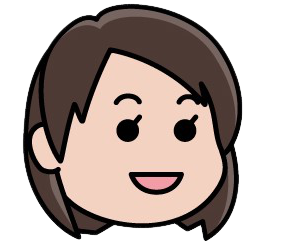
ケース別に検討していきます。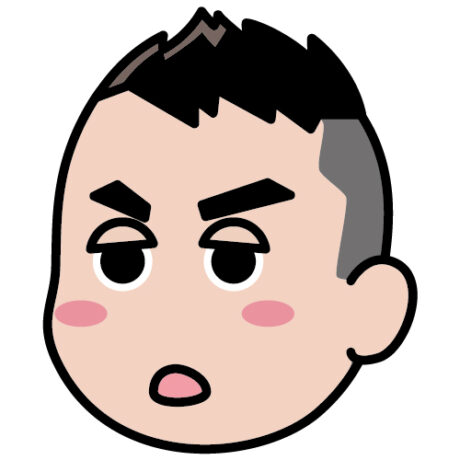
まずは前妻の子どもです。
生命保険を利用する
上記ポイントで指摘した基礎財産額を小さくする方法です。
生命保険において、契約者(被保険者)が亡くなると契約に基づいて受取人に指定された者が原始的に保険支払請求権を取得します。これを行使すると生命保険金が相続財産を経由せず保険会社から直接支払われることになるため、遺留分の対象にはなりません。
ただし他の相続人との間に著しい不公平が生じるような特段の事情が存する場合は例外的に遺留分の対象となります(最高裁平成16年10月29日判決)。特段の事情の有無については金額だけではなく、遺産総額に対する比率、同居の有無、介護等の貢献度合、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断することになります。
同居もせず被相続人との関係も希薄になった前妻の子どもであってもその生活が厳しく、一方で被相続人が財産の大部分を生命保険に充てていたような場合には遺留分の対象になり得ることに留意して下さい。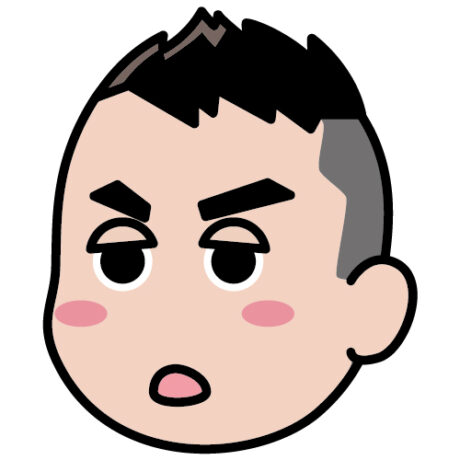
生前贈与を利用する
前妻の子ども以外の者に早めに生前贈与した上で、遺留分侵害額請求権の時間的限界を利用する方法もあります。
〇持ち戻し期間の制限
生前贈与自体は遺留分侵害額請求の対象となり、原則としてその受益分を基礎財産に計上(持ち戻し)して侵害額を算出しなければならないため、遺留分侵害額も増加することになります。
ただし事情を知らない第三者が相手であれば相続開始の1年よりも前に、相続人では10年よりも前に生前贈与すればこの受け戻しをする必要はありません(1044条)。
〇遺留分侵害額請求権の時効
遺留分権利者が相続開始と遺留分を侵害する生前贈与があったことを知ってから1年を経過すれば侵害額請求権は時効消滅し、相続開始から10年が経過した場合も時効消滅します(1048条)。
いずれの場合においても生前贈与はできるだけ早くに行うこと、そして消滅時効では遺留分侵害額請求された者が確実に時効の援用を行うことに注意が必要です。
遺言書
オーソドックスですが、自分の意思を忠実に遺言書に記すという方法は外せません。もちろん遺留分の問題は生じますが、遺言をせずに法定相続分がそのまま相続されることに比べれば取得分を抑えることができ、子どもが遺留分侵害額請求をしない可能性もあります。付言事項には遺留分侵害額請求を行使しないことを希望する旨を忘れずに記載しましょう。
〇遺産分割協議が不要となる書き方
遺言書には「全財産の3分の2は〇に、残り3分の1は△に相続させる」と割合だけを示す相続分の指定も可能ですが、「自宅不動産は○に、A銀行預金は△に相続させる」と全遺産について個別の相手を示す遺産分割方法の指定であれば、遺産分割協議を要しないため手続きが簡便です。
〇特別受益
もし、過去に前妻の子どもに対して比較的高額な学費援助や結婚資金提供等を行っていた場合は、その特別受益について遺言書に明確に付記します。特別受益額は遺留分侵害額から控除されるため、当該相続人が実際に受け取ることのできる金額が減ることになるからです。
相続人同士の争いが生じた場合、この遺言書の記載自体が特別受益があったことの証拠になりえます。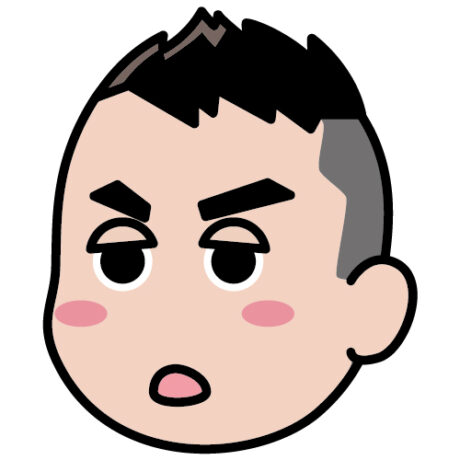
〇作成した遺言書は専門家に見てもらう
遺言書にはその様式についても細かな条件があり、特に自筆証書遺言では書き方によって遺言全体が無効となる場合があります。
一度専門家に見てもらうことをお勧めします。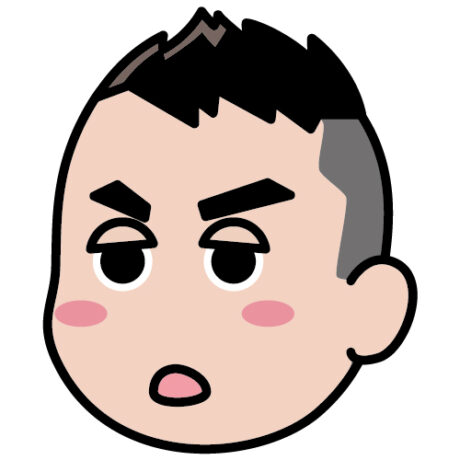
【ケース2】不仲の子ども 縁を切った場合等

【ケース1】と同様、生命保険、生前贈与、遺言を利用し、不仲、縁を切った子どもの遺留分に備えることが基本です。ここでは相続権が完全になくなる廃除について説明します。
廃除
相続人となる者に次の事由がある場合は家庭裁判所の手続きをとることによりその相続権を剥奪することができます(892条)。相続権がなくなれば遺留分も認められず、相続から完全に切り離すことが可能となるのです。
・被相続人に対する虐待または重大な侮辱
・著しい非行
廃除するには生前に家庭裁判所に廃除を申立てる、又は遺言書に書き記すという2つの方法があります。
ただし上記事由は単なる不仲というだけでは不十分であり、家庭裁判所の審判手続きにおいて家族関係が破壊され修復困難であると認められること、及びそれを裏付ける証拠も必要となります。これらの主張立証は生前申立では被相続人自らが、遺言廃除では遺言執行者が行います。
公正証書遺言
遺言書を利用する場合、自筆証書遺言にこれまでの非行を付記して廃除を希望する旨を記載することも可能ですが、より確実な方法として公正証書遺言で廃除の意思を示し、これに過去の暴力や侮辱の事実について詳細に記載した事実実験公正証書も合わせるとよいでしょう。公正証書は法律の専門家である公証人が作成するため、審判における主張立証を強く意識した書面となるはずです。
【ケース3】事業承継に参加しない子ども

事業承継においても生命保険や生前贈与は有効です。また遺言書は必ず準備し、事業用財産や株式等が後継者に確実に承継されるよう定めておかなければなりません。結果、遺産が後継者に集中しますが、他の相続人からの遺留分侵害額請求を招いてしまっては事業承継が頓挫しかねません。そこで遺留分対策が特に重要となるのです。
遺留分放棄
被相続人の生前であっても、遺留分権利者が家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます(1049条1項)。これにより相続開始後の遺留分侵害額請求の心配がなくなります。
しかし家庭裁判所への申立は遺留分権利者自らの意思で行う必要があり、その人にとってはメリットがないのに複雑な手続きを負担してもらえるのかという問題があります。
また家庭裁判所による許可・不許可の基準に微妙な点もあり、利用しづらいというのが現状です。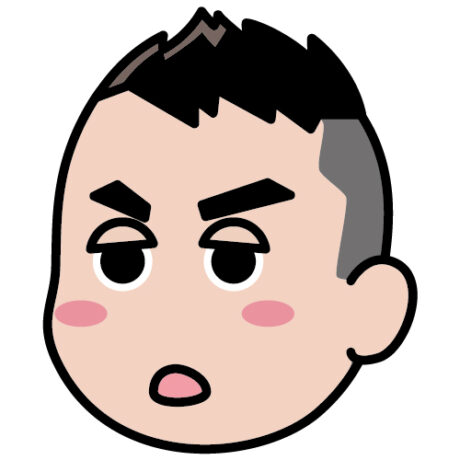
遺留分に関する民法の特例(経営承継円滑化法)
そこで経営承継円滑化法では、遺留分権利者に委ねるのではなく、後継者自らがとることのできる手続きが新たに設けられました。
具体的には、後継者と他の相続人全員との間で遺留分算定の基礎財産に関して以下の合意をすれば、後継者が単独で確認(経済産業大臣)、及び許可(家庭裁判所)の手続きをとることができます。
〇除外合意
遺留分算定基礎財産から贈与等された株式等を除外するもので、合意した他の相続人は遺留分の主張ができなくなります(経営承継円滑化法4条1項1号)。
〇固定合意
基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定するものです(同法4条1項2号)。この合意をすると株式等の価額が上がっても遺留分額には影響をしないので、想定外の遺留分の主張を防止できます。
なお合意時価額は弁護士等の専門家による証明が必要です。詳しくは当事務所の弁護士にお尋ね下さい。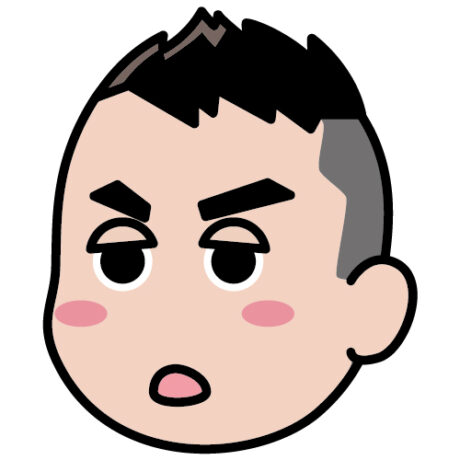
まとめ
早くから準備しておけば、諸事情により子どもに相続させないこともいろいろ対策できます。
相続の問題は、早くから専門家に相談し、最善を検討することが重要です。
気軽にご連絡いただければと思います。