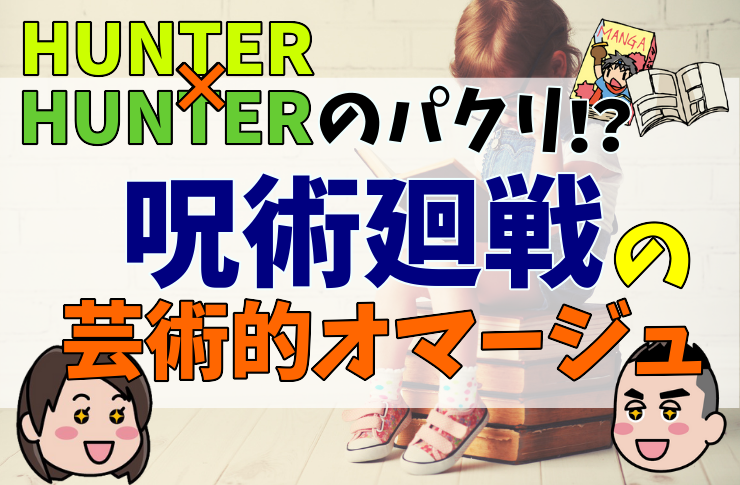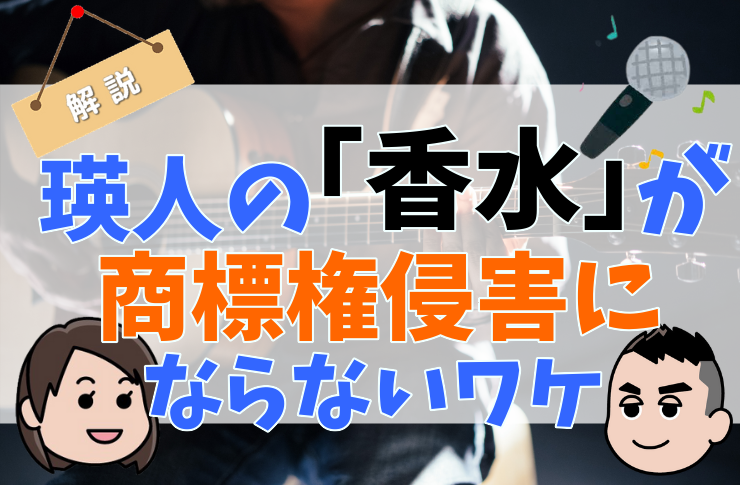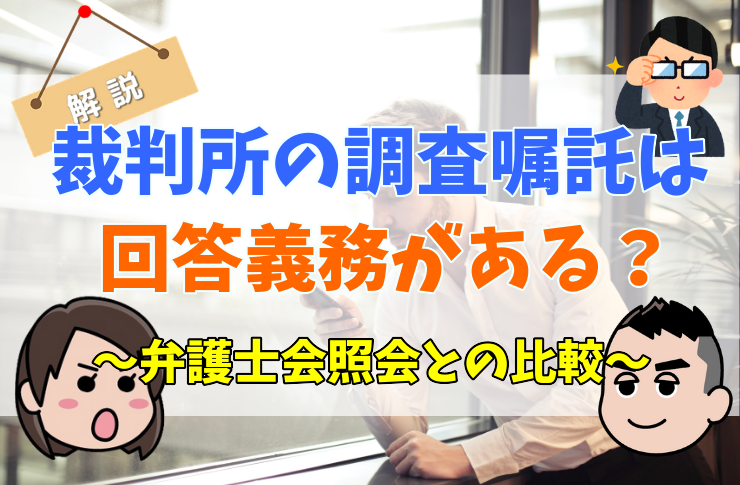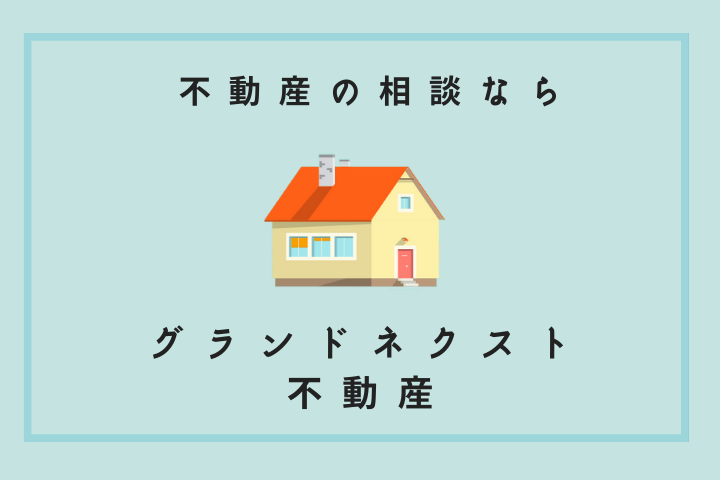離婚の際の夫婦の共有財産を分け合う「財産分与」(民法768条)においては、割合は同居期間に増えた財産の2分の1ずつとなるのが大原則です。
夫婦お互いの人格・役割を尊重した結論です。
しかし、かなり限定された場合ですが、この2分の1の割合が適用されない場合もあります。
①夫婦の一方配偶者に著しい浪費がある場合も2分の1なのか
②一方の配偶者の特殊な才能により財産が形成された場合
③一方の配偶者の特有財産が資産形成に大きく影響した場合
です。以下、解説していきます。
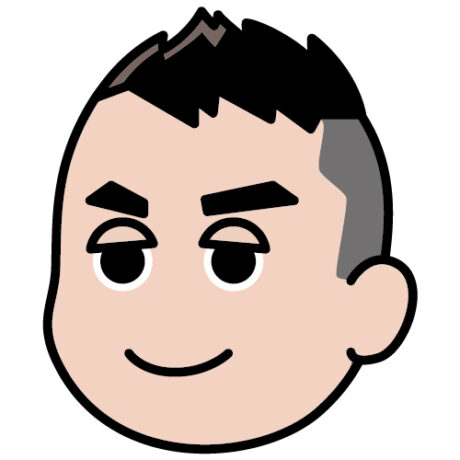
離婚事件をこれまでに360件以上解決している,千代田区・青梅市の弁護士法人アズバーズ代表弁護士であり、学校法人中央大学の法務全般を担当している弁護士の櫻井俊宏が解説します。
1 夫婦の一方配偶者に著しい浪費がある場合も2分の1なのか
一方の配偶者に著しい浪費がある場合は、2分の1ルールが修正される場合もあります。
これについては、水戸家庭裁判所の平成28年3月の裁判例が参考になります。
次のような事案です。
・夫婦は共働きで、夫の年収は900万円~1500万円程度、妻の年収が830万円であった。
・財産を開示したところ、夫の管理財産は、住宅ローンの他、カードローン等の負債が580万円あった。これらの負債を差し引いて、約200万円だった。
妻の管理財産は1億5000万円であった。
・妻は、夫による送金だけでは不足する生活費を維持するため、倹約に努めていた。
この事案では、2分の1ルールそのままだと,
200万円(夫管理)+1億5000万円(妻管理)/2=7600万円
ずつの取り分となります。
妻は既に1億5000万円分保有しているので、差額の7400万円を支払わなくてはならないことになります。
これは原則現金払いをしなくてはなりません。
この結論は、倹約にも努めてきた妻にあまりにも酷です。
そこで、裁判所は、妻の方が育児を含む家事労働の負担が大きかったこと、妻の1億5000万円の資産ができたことについて、その母親からの金銭的援助や相続も一定程度影響していることから、夫婦財産ができた貢献の割合を、
夫3割:妻7割
と判断しました。
ただし、この事案は、妻の管理財産が1億5000万円と多額であったこと、家事負担が多かったこと、財産が増えた過程・夫の浪費等から、そのまま2分の1とするとあまりにも公平が害されることから、特別に修正された事例であると言えます。
また、裁判所でこれが認められるためには、上記のように妻の家事負担が多かったことや、夫の浪費の事実を裏付ける証拠の提出が必要となってきます。
2 一方の特殊な才能により財産が形成された場合 医師・経営者
大阪高等裁判所平成26年3月13日判決は、夫が開業医の医師として医療法人を経営していた事案について、医療法人の持分を純資産価額約2億円の7割である1億4000万円とした上で、財産分与の割合について、
夫6割:妻4割
としています。
裁判所は、個人の尊厳と両性の本質的平等から財産分与の割合は原則として2分の1であると言及しました。
しかしスポーツ選手のように高額な収入が将来の生活費を前倒しで支払う意味合いがあるときや、高額な収入の基礎である特殊な才能が結婚前の個人的努力による場合は、そのような事情を航路することが個人の尊厳確保に繋がると判断しています。
この後者の事例と言うことになります。
前者のスポーツ選手の場合は、プロ野球選手等が典型的にわかりやすいでしょう。
プロ野球選手の場合、結婚後に取得した多額の契約金等は2分の1ルールに入らない可能性があるわけです。
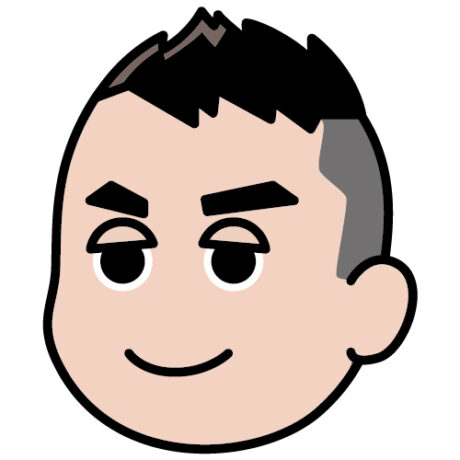
なお、この特殊な才能による場合については、なんと夫95:妻5という極端な分け方になった事例もあります。
すなわち、東京地方裁判所平成15年9月26日判決は、夫が一部上場企業の代表取締役であり、約220億円の財産があった事案です。夫の特殊な能力を大きく評価して、
夫95:妻5
として、それでも妻には10億の財産が分与されました。
スケールがすごい事案ですね。
3 一方の特有財産が資産形成に大きく影響した場合
特有財産とは、夫婦が同居する前から、持っていた財産のことを言います。
夫婦共有財産は、原則として、結婚の同居時から別居時に増えた財産のことを言うので、同居する前から財産は夫婦共有財産ではない、その特有の財産ということです。
ただ、この特有財産主張は、原則として、預金なら預金、物なら物と、同居時から別居時まで形を変えないで残っている場合でないと認定されないので、立証がとても難しいです。
東京高等裁判所平成7年4月27日判決は、夫婦名義のゴルフ会員権の購入代金の大部分が、夫がもともと持っていたお金(特有財産)から多く支出された事案です。
財産分与割合は、
夫64:妻36
となりました。
このように当初あった物が、現金等の流動資産に転換したとしても、特有財産が資産形成に影響したことが明らかである場合は財産分与の割合が修正されることがあります。
しかし、同居時に特有財産主張するために財産が存在していたことの立証は、しっかりとしていく必要があります。
4 一方の配偶者が有責配偶者でも「2分の1」?
一方の配偶者が不貞をした等の有責配偶者でも2分の1ルールが適用されるのでしょうか?
まずは財産分与に関するルールを確認します。
清算的財産分与の目的
婚姻生活では性別分業による格差が生じ得ます。すなわち、片働き夫婦であれば職業労働を担当する夫の所得能力が増大する一方で家事労働を担当する妻の所得能力は減少する、また、共働きの妻も夫以上に家事労働を担うことが多く夫ほど資力を増やし得ないという不平等が生まれやすくなります。こうした格差を離婚時に是正すべく、共有財産の清算である財産分与については、2分の1ルールが家庭裁判所の実務となっているのです。
したがって専業主婦(夫)で無収入であっても、財産分与によって共有財産の2分の1を取得することができます。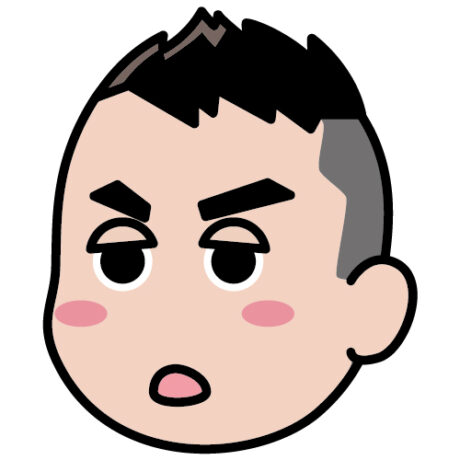
有責配偶者でも平等
いずれか一方が離婚原因を作ったことと離婚時までの財産形成とは何ら関連性がないのが通常ですので、有責性が財産分与の割合に影響を与えることはありません。
この点、東京高判平成3年7月16日も有責配偶者(不貞行為)からの財産分与請求を認めています。
したがって「あなたのせいで離婚するのだから、財産は全部もらう」といった主張は通らなくなります。
なお、婚姻費用については、有責配偶者でも基本的には婚姻費用の請求が認められます。しかし、例えば、不貞をしたことが証拠をもって明らかであり、その不貞が離婚の主たる原因であるような場合には、自分の生活費分の婚姻費用の請求が認められない場合もあります(東京家庭裁判所平成20年7月31日審判例等)。
5 まとめ
以上のように、財産分与は、かなり限定的な場合ですが、2分の1ルールが修正される場合もあります。
これからは婚前契約で財産分与について合意していくことも意味があるかもしれません。
【関連記事】
離婚調停において気をつけることについて